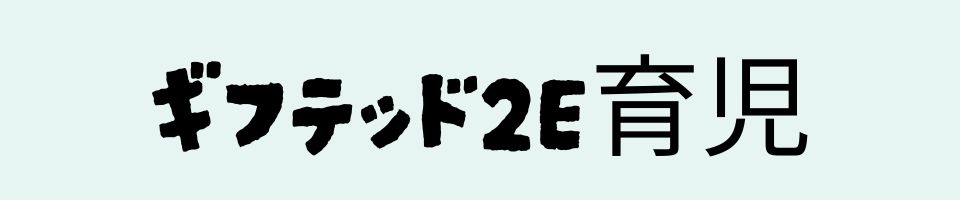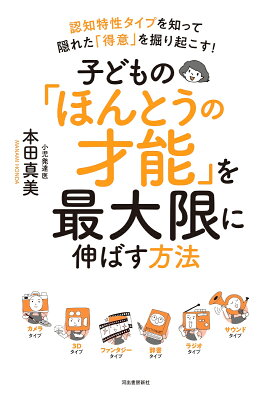「視覚優位」と「聴覚優位」という言葉はなんとなく聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。これらは「認知特性」といわれ、この他に「言語優位」「体感覚優位」の主に4つがあるとされています。

ASD(自閉症スペクトラム)は視覚優位が多いと聞くけれどうちの子はどっちかわからない
これは実際に育てていて私自身が感じたことなのですが、息子は検査により、発達障害の診断名は付かないものの、ASD傾向があると言われていました。支援方法を調べていく中で、ASDの場合は「視覚優位」が多いという記事をよく目にします。
ただ、生活を見ているとどうも聴覚優位な部分が多いのでどっちの支援をしたら良いのだろうと思っていました。
以前ギフテッドには大きく6つのタイプに分けられ、タイプ別に支援方法が異なるとお伝えしました。
今回の「認知特性」についてもお子さんがどちらの傾向があるかを知ることで、支援につながる可能性があります。
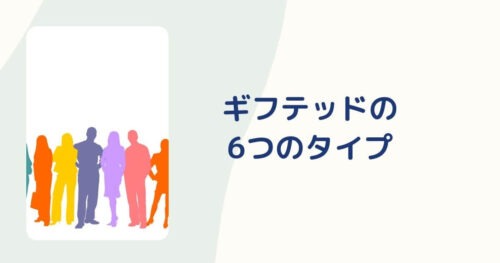
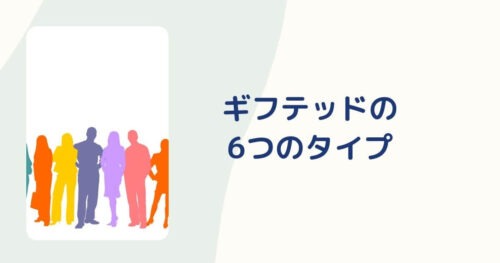
この記事では、認知特性のうち、視覚優位、聴覚優位、言語優位の特徴や、困りごとへの対処方法や、特性を活かす方法について説明します。
認知特性とは
認知特性とは、見る・聞く・読むといったインプットと、それを理解・整理・記憶する処理、そしてそれらをもとに書いたり話したり表現するまでの、一連の方法と、人によって異なるその偏りのことを言います
引用元 本田式認知特性研究所
情報処理の方法は人それぞれ「認知特性」によって異なるため、学校の授業でどちらかに偏った指導法だった場合、意思疎通などが上手くいかない原因になることがあります。
認知特性は、大きく4つに分けられます。
視覚優位 目から入ってくる情報の方が処理するのが得意
聴覚優位 耳から入ってくる情報の方が処理するのが得意
言語優位 読んだ情報を処理するのが得意
体感覚優位 触感や動きを通じて情報を処理するのが得意
発達障害の子どもの中には同じ診断名であったとしても、認知特性が異なるタイプがあるために、教育現場では子どもたちの理解や指導に混乱が生じているとされています。
認知特性においては、発達障害の診断名は手立てにはならないのです。これが私自身も戸惑った原因でもあるのですが、自閉症スペクトラム(ASD)だからと言って必ずしも「視覚優位」とは限りません。
認知特性を知るメリット
認知特性を知ることで、学習方法やコミュニケーション方法において最も自分に適している方法に気づくことができます。その結果、効率よく学習できたり、コミュニケーションがスムーズにいくでしょう。
ギフテッドだから「なんでもできる天才」というわけではなく、極端な認知特性があり、困難を抱えている人も多くいます。
例えば、視覚優位にも関わらず、図やイラストなどの描写なしで口頭だけで解説をされたとしても理解が進まない可能性があります。もし自身の特性を知っていれば、図を描きながら説明をしてもらうようにお願いすることもできます。
逆に、聴覚優位の場合は、目からの情報だけではなく、耳からの情報も入れてもらうことで理解しやすくなることも。
このように、学習の支援の一つとして認知特性を活かすことも可能です。
視覚優位とは
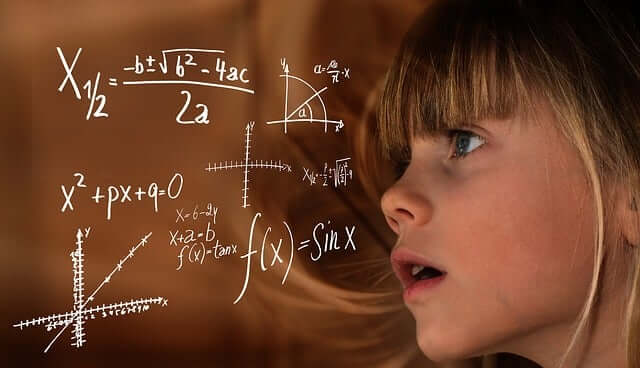
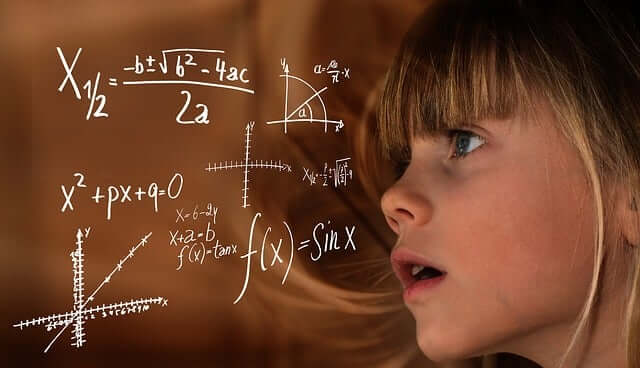
視覚優位の2つのタイプ
視覚優位の中でも細かく分けると2つのタイプがあると言われています。そのため同じ視覚優位だと思っていても、得意なことは異なるとされています。
- 視覚優位:写真(カメラアイ)タイプ
写真のように、2次元で捉え思考するタイプ
アニメの脇役のキャラクターの似顔絵も描ける - 視覚優位:3次元タイプ
空間や時間軸を使って考えるタイプ
映像として物事を記憶する
「写真(カメラアイ)タイプ」の特徴と学習支援
おすすめの勉強方法は、文字だけだと理解しづらいことがあるため、写真やイラストが多く、視覚的に訴える教材が良いとされています。イメージなどを使うと覚えやすいので、見て遊びながら学べるカードゲームがおすすめ。
通信教育を使用する場合は、カラフルな色使いとキャラクターが登場する「進研ゼミ小学講座」
![]()
![]()
「進研ゼミ小学講座」
![]()
![]()
「3Dタイプ」の特徴と学習支援
学習支援としては、文字だけで理解するよりも、映像や動画を使った方が理解がしやすいとされています。
通信教育も同様に映像や動画があるものがおすすめ。すらら![]()
![]()
Z会の通信教育 小学生コース
![]()
![]()
すらら
また、共通の視覚優位の支援の方法として、視界に余計ななものが入らないように環境を整えることも一つです。
聴覚優位とは


聴覚優位の2つのタイプ
聴覚優位の2タイプはこちら。
- 聴覚優位:聴覚言語(ラジオタイプ)
文字や文章を「音」として耳から入れ情報処理するタイプ
英単語を覚えるときは何度も聞いたり暗唱をして覚える - 聴覚優位:聴覚&音(サウンドタイプ)
音色や音階といった音楽的イメージを理解・処理できるタイプ
絶対音感がある
「聴覚言語ラジオタイプ」の特徴と学習支援
おすすめの学習方法は、通学時間などにイヤホンで聴くなど、目で見るより耳から学習すること。ただし、漢字などは同じ読み方の漢字を間違えることが多いので重点的に意識をして取り組むようにします。
声に出して覚える漢字カードはピッタリです。
聞く読書のAmazon Audibleやオーディオブック聴き放題 - audiobook.jp
![]()
![]()
「サウンドタイプ」の特徴と学習支援
英単語や歴史など暗記をするときは、独り言のようにぶつぶつ言いながら耳で聞きながら覚えると効果的です。音楽的な音色やリズムで聞いた情報を認知するのも得意なので、リズムに乗せながら暗記するのも良いかもしれません。
聴覚優位の共通の学習の支援としては、講義型の動画や、リスニング教材、ラジオ講座など聴覚的な情報で学ぶのが効果的。また、雑音のようにうるさすぎると勉強に集中できないことも。視覚優位同様、環境調整も支援の一つです。
たった35日でうちの子が英語を話した!楽天4部門1位の英会話!<七田式>通信教育では、上記のようなCDを使った英語学習などは効果的です。
下記の英熟語図鑑は、音声が無料ダウンロードができます。得意な聴覚に加えて、可愛いイラストで視覚的にも訴えながら覚えることができます☟
言語優位とは
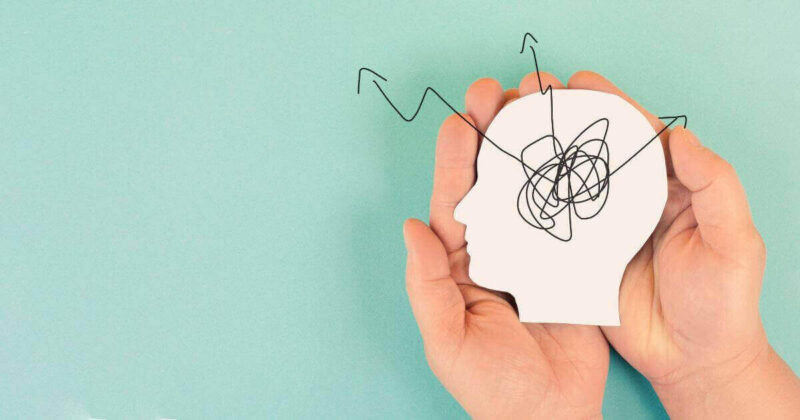
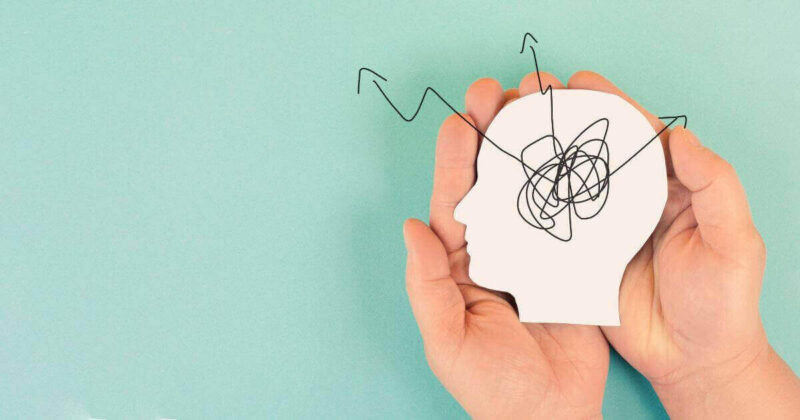
言語優位の2つのタイプ
言語優位の二つのタイプはこちら。
- 言語優位:言語映像(ファンタジー)タイプ
読んだり聞いたりした内容を映像化して思考するタイプ
イメージを言語化できる - 言語優位:言語抽象(辞書)タイプ
読んだ文字や文章をそのまま言葉で思考するタイプ
英単語などは書いて覚える
「言語映像タイプ」の特徴と学習支援
文字を読んでイメージしたり、イメージを言葉にするのが得意なのでストーリー仕立てで学ぶのが効果的。英単語は、その言葉を実際に使っている場面を想像しながら言葉と映像を結びつけて覚えていきます。
「言語抽象タイプ」の特徴と学習支援
文字で書いたり見たりして覚える方法が効果的。また、言語化や図式化が上手なので、ノートにまとめながら学ぶと良い。 歴史などは語呂合わせや家系図、相関図などを書いて覚えます。
言語優位タイプに共通する学習方法として、映像付きの通信教育よりは紙、もしくはタブレットのみの教材の方が向いているかもしれません。動画を見るよりも、自身で教科書や参考書を読んで文字から理解した方が学べることもあります。
通信教育を使う場合は、紙ベースの教材や「スマイルゼミ」
![]()
![]()
![]()
![]()
認知特性テスト
こちらの「医師のつくった「頭のよさ」テスト 認知特性から見た6つのパターン (光文社新書) [ 本田真美 ]」では質問形式でどのタイプが優性か知ることができます。
Kindle Unlimitedでは無料で読むことが可能です。
中学生くらいから答えることはできると思います。どうしても息子がどっちの認知特性なのかわからなかったのですが、この認知テストでとても理解ができました。
大人の認知特性テストは、子供では答えるのがが難しい問いもあります。こちらは2024年3月27日に発売されたばかりの子ども用の認知特性を理解するための本です。
わが家のギフテッド2E児の認知特性は
上記のチェックリストによると、わが家のギフテッド2E男子の場合、圧倒的に「聴覚優位のサウンドタイプ」でした。
この結果自体は想定内であり、やっぱりそうだよねと思ったのですが、そうなると数年前にWISCを受けた時に、実際に検査をしてくださった心理士さんから言われた言葉が引っ掛かります。
以前「IQはいくつからギフテッド?2E児のWISC−4でわかること」の記事内で記載していますが、



聞いて処理するよりも視覚的に見て考えるほうが得意なのでスケジュール表などを利用する。但し情報量が多すぎるとどこに注目したらよいかわからないため、シンプルなほうが良い。
視覚刺激を提示する際は、情報量を絞って、言葉での説明を加える。手順を示し続けてワーキングメモリの弱さに配慮する。
「聴覚優位のサウンドタイプ」なのでこれは当てはまらないのではないか。と思われるかもしれませんが、実際小学生の頃は1日のスケジュール、やることを見える化することでスムーズにいくこともあったのも事実。
壁に貼り紙をしていましたが、ワーキングメモリの弱さや実行機能の弱さには視覚的に訴えることはとても効果的でした。
この辺りが腑に落ちなかったのですが、調べていくうちにとても興味深い文献を見つけました。
こちらの文献では自閉症スペクトラムにおける「視覚優位」という言葉の曖昧さについて述べています。
視覚的情報は一過性ではなく安定していることが多いこと,注意を向けやすいこと,反復参照可能なので記憶しなければならないという負担が少ないことから,聴覚的情報(特に音声言語)よりも処理しやすい。つまり個人の処理能力の優劣ではなく,処理しやすさについての情報の側の優劣と言うべきではなかろうか。つまり「視覚的支援」の有効性を言うために 「視覚優位」という言い方がされるようになったのであろう。
〜中略〜
筆者は,自閉症スペクトラムの人の視覚情報処理能力が絶対的に優れているというよりも,視覚的支援が実際に効果的なので,視覚的情報の方が聴覚的情報よりも処理しやすいという点で優位に立つという意味だと考えている。
引用元 自閉症スペクトラムにみられる「視覚優位」門 眞一郎
つまり「視覚的な支援」の方が「聴覚的な支援」よりも効果があるという意味での「視覚優位」ではないかとしています。
確かに、私が上記のように言われたのはWISCの検査後に心理士さんから支援方法として言われました。支援方法として「視覚的な支援が優位」という意味では納得できます。
「視覚優位」という言葉の意味を理解した上で、支援をする必要があります。
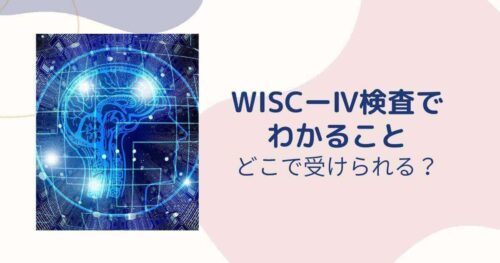
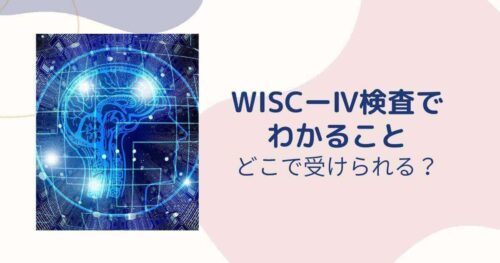
そんな息子の独特の勉強方法に関しては前回の記事でもお伝えしましたが、聴覚を使って暗記をするのが得意です。
圧倒的に「聴覚優位」とはいえ、息子は2歳ごろからカメラアイの能力があります。風景の記憶が写真として蘇ってくると言っているので視覚優位の要素がゼロというわけではありません。ただし、このカメラアイに関しては、息子の場合は勉強では使えないそうで、見たからといって暗記はできないそう。
暗記をする場合はひたすら口で唱えながら時には同時に書きながら覚えると言っていました。
このように、ギフテッドの場合は、簡単に「〇〇優位」という一言では済まさないように思います。息子の場合に関しては、色々な特性が作用しあって独自の学習方法を身につけている気がします。
こうだからこう、と決めつけるのではなく、一つ一つの困りごとの症状を見て対応することで生活がしやすくなるのではないでしょうか。


ちなみに私は「言語優位」なので、言葉から理解することが得意です。初対面の人の顔を覚えるのは苦手で、名前(字面)で覚えていることも。英単語や漢字などはひたすら書いて覚えるタイプでした。暗記系は語呂合わせが好きだったのも納得です。
認知特性もある程度は生まれつきとされていますが、私と息子とでは認知特性は異なります。
支援の参考に
いかがだったでしょうか。私自身、育てていて息子には視覚優位な部分もあるため、どっちなのだろうと疑問だったのですが、「聴覚優位」が突出している場合でも、他の認知特性がゼロというわけではないこともわかりました。
また「視覚優位」と「聴覚優位」だけだと思っていたところ「言語優位」も加わることで、私自身はどちらもあまりピンときていなかったのでとても腑に落ちるところがありました。
以上、認知特性についてでした。「視覚優位」「聴覚優位」は聞いたことがあるもののどんな特性なのか疑問を持たれていた方のお役に立てたら幸いです。
続いて、情報処理の特性についてはこちらも是非☟
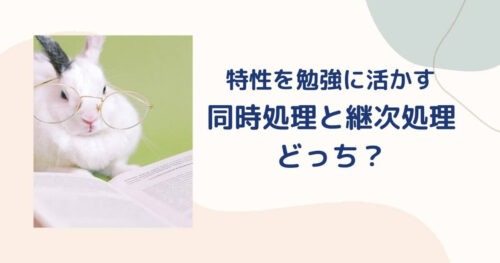
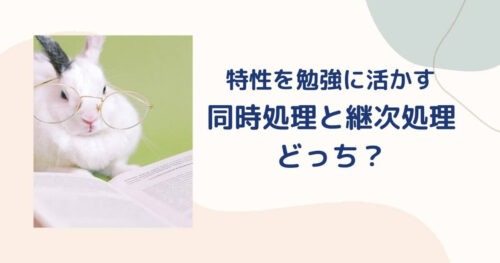
参考書籍
・ギフテッド 天才の育て方 (ヒューマンケアブックス)
・医師のつくった「頭のよさ」テスト~認知特性から見た6つのパターン~ (光文社新書)
・子どもの「ほんとうの才能」を最大限に伸ばす方法: 認知特性タイプを知って隠れた「得意」を掘り起こす!