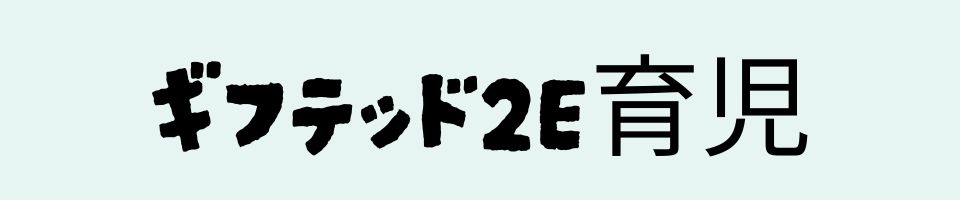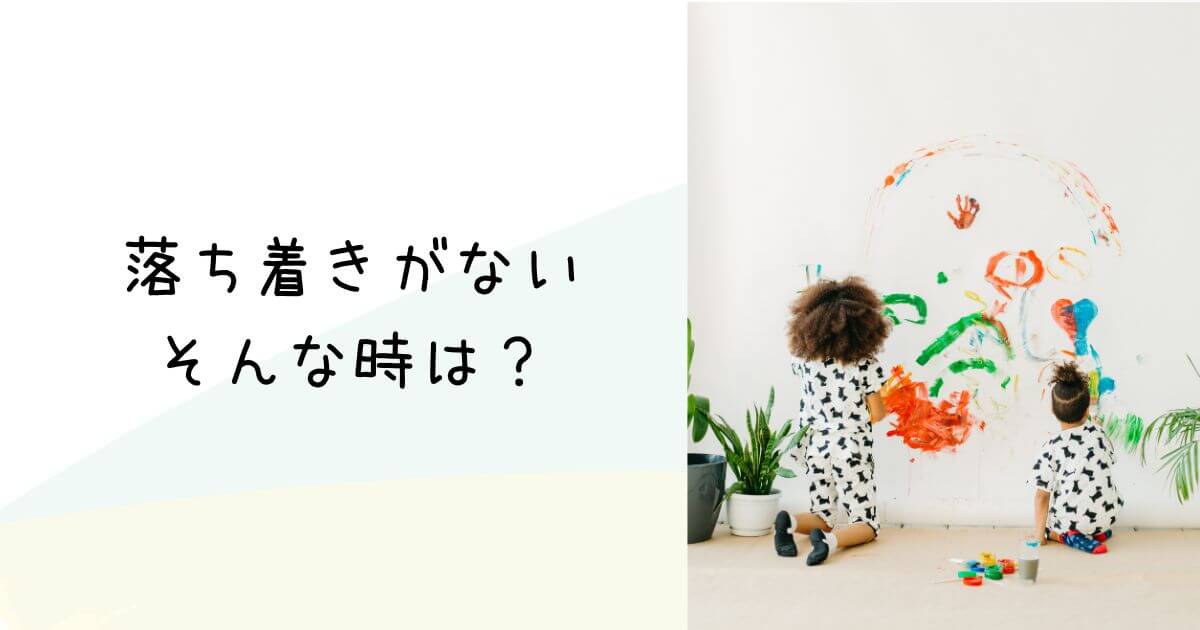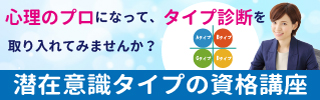- 心が落ち着かない子をどうしたら?
-
マインドフルネスを親子で実践してみました。視点を変えてみるのも大切です。マインドフルネスでEQ(心の知能指数)を高めることもできます。
「何をやっても効果なし!お手上げ状態」のときに取り組んでみたことシリーズ第二弾。アンガーマネジメントの次はマインドフルネスについてです。
育児や仕事でイライラして心が落ち着かない、発達障害や発達特性のあるお子さんを育てていて心身ともに疲れている、そんな方には是非実践してほしい方法の一つです。毎日関わっておられるご両親や先生方はもちろんですが、お子様も実践できるのがマインドフルネスです。
私自身、ヨガの資格「全米ヨガアライアンスRYT200」を数年前に習得しています。ヨガの中でも、瞑想やマインドフルネスといった単語はよく出てくるので耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
でも、一体それが何なのか、「瞑想」と「マインドフルネス」の違いは何なのか、そしてどんな効果があるのかというところまでご存じない方もいらっしゃると思います。
企業の研修でも使われるマインドフルネスですが、育児で疲れ果てているお母さんや、発達特性があり落ち着かないお子さまなどにもおすすめです。
そんな育児にも使える「マインドフルネス」について今回はご紹介します。
「マインド」というと少し身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、決して怪しいものではありませんので安心してくださいね。以前ヨガについては少し触れているので合わせてどうぞ。

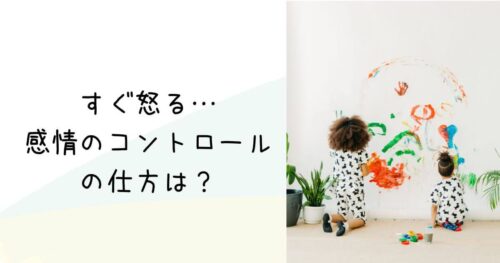
こちらの「ギフテッド児のお悩み別Q&A」のカテゴリーでは、実体験に基づいた筆者なりの考えをまとめています。
今まで、数々の医療機関・専門機関を受診して受けたアドバイスや、専門書に基づいて実際にやってみてうまくいったこと、いかなかったことについて記載しています。
ギフテッド児もさまざまなタイプがいるため、その子によっては効果がない場合もございます。その旨ご理解の上、参考にしていただければ幸いです。
マインドフルネスという言葉の意味とは?
現在において起こっている経験に注意を向ける心理的な過程。
引用元 Wikipediaより最終更新 2023年5月6日 (土) 05:19
定義としては「今この瞬間の体験に意図的に意識を向け、評価をせずに捕らわれのない状態で、ただ観ること」
Wikipediaはこうありますが、ちょっと抽象的でわかりづらいと思います。
簡単に言うと、「今ここに意識を向けること」です。すると「気づき」があるはずです。その浮かんできた気づきに対してジャッジせず、全てをあるがままに受け入れていきます。
例えば、目をつぶると様々なことが頭に浮かぶはずです。
朝なかなか学校の支度をせずイライラしたなあ。またイライラが蘇ってきたな。雨降るかしら。この後買い物に行こうかな。夜ご飯は何にしよう…などなど思考は止まりません。
マインドフルネスは意識をここに向けることなので、未来や過去に意識がいってしまったら、「今」に意識を向けます。
これを繰り返し、意識を今に向けられるようになると徐々に心が落ち着いてくるのを感じられるようになります。
子どもとやって見ようと思ったきっかけ
大分前にヨガのクラスでも何度か私自身「マインドフルネス瞑想」のクラスを受けたことがあります。「自分の心があっちこっちに動いていることに気づく」という経験を初めてし、とても不思議な感覚でした。そして、「今ここに意識を向けること」の難しさも体感しました。その後、その感覚に慣れてくると、心が落ち着き、とても穏やかになることがわかりました。
海外生活をしていたころ、息子は心が常に荒波のようでした。
一緒に暮らしているこちらもとても心が休まる瞬間がなく、緊張した日々でした。同時に早めの反抗期に足を突っ込んでいたため、親の言う事はほぼ聞きませんでした。
私自身、余裕がなくなると数分でもヨガのポーズをとってみたり、呼吸を整えたり、というのは日常的にしていたはずなのですが、本当にいっぱいいっぱいの時は無気力状態に陥っていました。更に、頭の中はぐるぐる思考が止まらなかったり、未来を考えて絶望したり…まさにマインドフルネスとは真逆のマインドフルネスではない状態の「マインドレスネス」状態に陥っていました。
それでも「なんとかしたい」という自分自身の気持ちと、マインドフルネスによって得られる効果も実証済みだったので、こういうのがあるけど一度やってみる?という感じで息子を誘ってみました。
マインドフルネスの効果 うつや不安障害、発達障害にも
マインドフルネスを実践したからと言って、何かが劇的に変わるわけではありません。
しかし、継続して続けることで、抑うつなどの症状が改善するとも言われています。実際に、マインドフルネスストレス低減法やマインドフルネス認知療法は、うつ病や不安障害、などの精神疾患の治療に適用されることもあるようです。
また、発達障害のADHD特性を持つ成人と青年に対して、マインドフルネス瞑想を行った研究もアメリカや日本でもされています。
8週間のマインドフルネストレーニングプログラムの結果、ADHD 症状の改善、不安やうつ状態の改善が見られたそうです。
マインドフルネスによって、様々な効果が得られます。その効果のうちの一つ、「EQ」は自分の感情をうまく管理し利用できる能力のことで、「心の知能」とも呼ばれます。このEQを高めるのにもマインドフルネスは効果的と言われています。
EQとは?
IQとは、Intelligence Quotientの略で、知能指数のことで頭の回転の速さや記憶力の良さなど、IQについてはこちらのサイトではよく登場しますが、実は人生に与える影響はIQよりもEQのほうが大きいと言われます。
EQとは、「感情を扱う能力の高さ」を表します。Wikipediaによると以下のようにあります。
心の知能指数(emotional intelligence quotient、EQ)は、心の知能 (emotional intelligence、EI) を測定する指標である。心の知能とは、自己や他者の感情を知覚し、また自分の感情をコントロールする知能を指す。
比較的新しい概念のため、定義はいまだはっきりとしていない。
Wikipedia
マインドフルネス瞑想のやり方
やり方はいくつかあるのですが、初めての方や初心者の方は、マインドフルネスを学んだことのあるインストラクターや講師の方と行うのをおすすめします。息子も私がやるよりインストラクターにお願いした方が良いと思い、ZOOMでつないでオンラインで「マインドフルネス瞑想」のクラスを受講しました。
呼吸瞑想法
基本となる瞑想は、姿勢を正して座り、軽く目を瞑って、呼吸に集中します。呼吸は秒数にこだわらず楽な呼吸でゆっくり行えば大丈夫です。1日1回1分でもかまいません。そして30分以上集中できるようになるまで少しずつ時間をのばしていきます。
吐く息は副交感神経とつながっており、リラックスしているときに優位になる自律神経です。息をゆっくり吐くことによって心を静めていきます。
ボディー・スキャン
仰向けになり目を閉じ、意識を呼吸に向けながら、体の部分にも順番に向けていきます。足先からふくらはぎ、太もも、胴体、背中、両手の指先から肩、首から顔、後頭部、最後に頭頂へと意識を移動させています。注意を向けている部位が感じている感覚や、呼吸などを感じていきます。
歩行瞑想法
歩行瞑想法は、家の中はもちろん外でもできる歩きながら行う瞑想法です。かかとを床につける、つま先が上がる、など足の裏の感覚や重心を意識していきます。意識が逸れてしまったら、呼吸や足の感覚、自分の内部に生じてくる感覚に集中します。この瞑想法のメリットは日常生活の中で取り入れやすいということです。
その他にも「食べる瞑想」「書く瞑想」などがあります。食べる瞑想は「レーズンメディテーション」が有名で、一粒のレーズンを五感を使って味わう瞑想です。
たくさんあるとどれをやればいいのかわからないかもしれませんが、どれでも取り組みやすいもので良いと思います。
マインドフルネスと瞑想の違い

ここまで読んでいただくと、「マインドフルネス」と「瞑想」の違いもおわかりいただけたのではないでしょうか。マインドフルネスが「今」に集中する状態のことで、瞑想というのは、マインドフルネスに到達する方法、手段の一つとなります。「ヨガ」は動く瞑想とも言われています。
おすすめマインドフルネスの本

マインドフルネスの本は様々な種類が出版されています。大体やり方や効果などは同じことが記載されているので、どういった内容を知りたいかで選ぶと良いと思います。今回は「お子様向け」「まるでインストラクションを受けているように読める本」「マインドフルネスについて基礎から学ぶ本」3冊をご紹介します。
心が落ち着き、集中力がグングン高まる! 子どものためのマインドフルネス
イラストもかわいく色彩も豊かなので、絵本のようにお子様と一緒に楽しめます。雲や木になってみたり、子ネコの背のびやクマさんの呼吸をやってみたり…。幼稚園くらいのお子様から小学生低学年くらいのお子様でも簡単にできる、30のマインドフルネスエクササイズが載っています。お子さまと一緒に大人の親の方も、心と体をコントロールする方法を身につけられる、おすすめの一冊です。
こころが軽くなる マインドフルネスの本
こちらは、私自身が初めて手にしたマインドフルネスの本です。誰かにインストラクションをしてもらわなくても、読んでいるだけでマインドフルネスのクラスを受けているかのように優しく語りかけてくれる本です。初心者の方にもお勧めです。
マインドフルネス瞑想入門
こちらも先ほどと同じヨガインストラクターかつ一般社団法人マインドフルネス瞑想協会代表の吉田昌生さんの著書です。こちらは詳しく瞑想のやり方が書かれているので、詳しく論理的に学びたい方にお勧めです。付属CDつきなので音声に合わせて瞑想することができます。
3冊目はkindle unlimitedに登録すれば今なら無料で読めます。付属の「瞑想誘導CD」もkindle版のリンクから無料でダウンロードすることができます。
イラスト版 子どものマインドフルネス: 自分に自信が持てる55のヒント
アンガーマネジメントの記事でご紹介したシリーズから、なんとマインドフルネス版が7月に出版されます。まだ、中身は見ておりませんが、アンガーマネジメントの本同様きっとわかりやすくイラストを交えて説明がしてあるのだと思います。発売後手に取ってみようと思います。
まとめ
アンガーマネジメントといい、マインドフルネスといい即効性はありません。継続的に行うことで徐々に効果が表れてくるものです。毎日マインドフルネス瞑想の時間を取るのは難しい、という方も10分ないし5分あればできるのがマインドフルネス瞑想です。
こちらのサイトをご覧いただいている方の中には、育児に感情も心も振り回されている!という方もいらっしゃるかもしれません。
マインドフルネス瞑想もアンガーマネジメントも、続けていると思考や感情に振り回されなくなります。その結果、悩みや不安に思いを巡らせることが減っていくはずです。
こちらのサイトをご覧くださっている方のこころが少しでも楽になりますように。