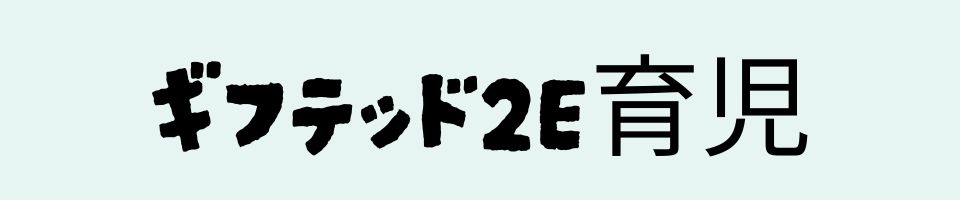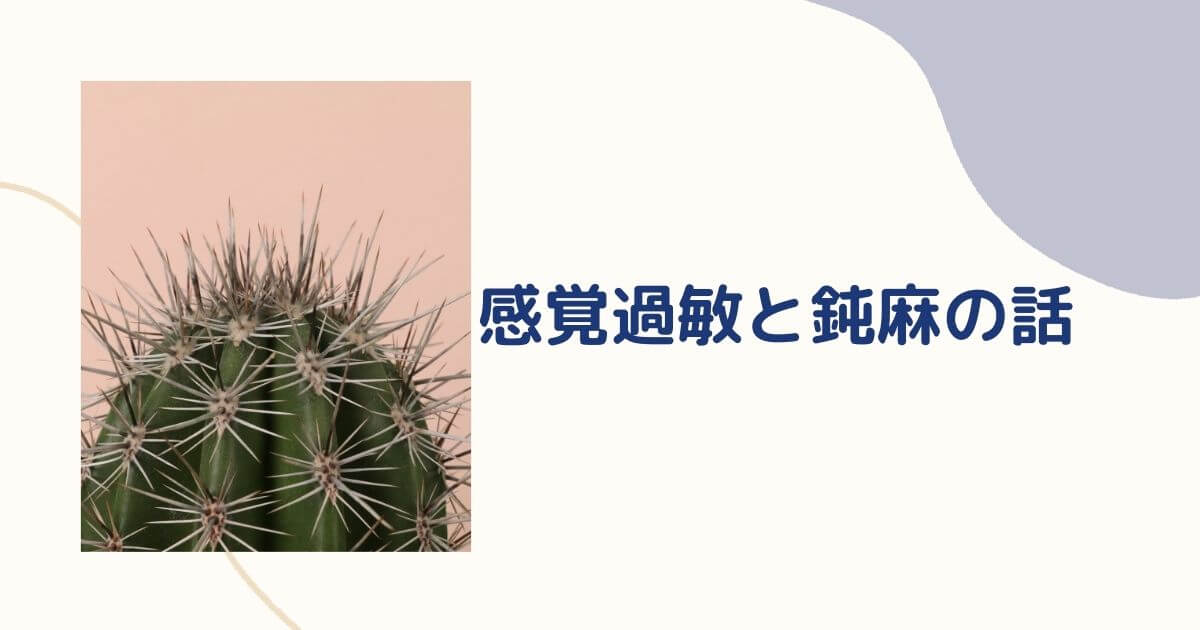今日は感覚にまつわる話です。
ギフテッドや発達障害の子は感覚が過敏だというのはよく聞く話かもしれません。
また、生まれつき感覚が過敏な性質を持っている、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)いわゆる「HSP」という言葉もよく耳にするようになりました。
症状が似ているため、区別をつけにくい印象がありますが、これらは「異なるもの」です。
今回は感覚過敏だけではなく、感覚鈍麻についても取り上げています。
ここであげる例はあくまでも我が家の一例となりますので、ご了承の上お読みいただければと思います。
ギフテッドとHSPは似ている?
まず、「ギフテッド」も「HSP」も病名や疾患ではない、という点では似ています。
また、ギフテッドの特性の一つであるOE(過興奮性)とHSPの特性も似ています。
ただ、「ギフテッド」と「HSP」はイコールではありません。
息子の例を挙げると、息子は「ギフテッド2E」と認定されていますが、HSPではありません。また、感覚に関しては、過敏さと鈍麻の両方を持っています。
どういうこと?と思われるかもしれませんが、これらはイコールではないのでこのようなことが起きてもおかしくはありません。
一つ一つ特徴についてみていきます。
感覚過敏とは
感覚過敏(かんかくかびん)は、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などの諸感覚が過敏で日常生活に困難さを抱えている状態である。感覚過敏は病名ではなく症状である。
Wikipediaより
聴覚の問題
(1) 泣き声や電子音など特定の音が苦手
(2) 同時に複数の人が話している場合に会話の聞き取りが困難
(3) 周囲の雑音など注目すべき音以外が大きく聞こえてしまう
(4) 大きな音が苦手
(5) 突然生じた(ように感じられる)音が苦手
視覚の問題
(1) 強い光やチカチカした光が苦手(まぶしさ)
(2) 同時に来る複数の視覚刺激がつらい
(3) 色や形など特定の苦手なものがある
(4) 読みの困難
(5) 見え方の異常(奥行がわからない、ぼやけや揺れなど)
触覚の問題
(1) タグや縫い目が皮膚にあたると苦痛であるなど服に関する問題
(2) 水や粘土など特定の苦手なものがある
(3) 人と接触するのが苦痛
(4) 痒みなどの問題
嗅覚の問題
(1) タバコや香水など特定の苦手なものがある
(2) 同時に来る複数のにおいがつらい
味覚の問題
(1) 苦手な食感がある
(2) 苦手な食べ物がある
(3) 苦手な味がある
これらはイメージしやすいのではないでしょうか。感覚過敏の場合、五感に関する刺激を過敏に感じてしまうという特性です。
感覚鈍麻とは
感覚鈍麻とは、味覚や痛覚などの感覚が極端に鈍い状態のこと。程度に個人差はあり、生活に支障が出るほど感覚が鈍い状態のケースもある。
- 触覚:暑さ・寒さや痛みに鈍感
- 味覚・嗅覚:においが分からない/濃い味を好む
- 聴覚:音に対する反応が鈍い・遅い
- 平衡感覚:揺れや傾きの調節が苦手
- 固有感覚:動き回りよくぶつかる
こちらはなかなかイメージがしにくいかもしれませんが、息子の場合は上記で言うと痛みに鈍感です。0歳から始まる予防接種では一度も泣いたことがありません。
感覚過敏は発達障害なのか
「感覚過敏」「感覚過敏」は病名ではありませんが、自閉症スペクトラム(ASD)の診断の一つに感覚過敏や鈍麻があると米国精神医学会の診断基準(DSM-5)に記載があります。
また、国立障害者リハビリテーションセンターは、発達障害のある人の感覚の問題を調査したところ、感覚の問題が最も顕著なのは聴覚であるが、自閉スペクトラム症(ASD)のある人では触覚の問題も無視できないことを発表しています。
発達障害の場合、感覚過敏であることが多いとされていますが、感覚過敏があるから発達障害、発達障害があるから感覚過敏があるというわけではありません。
またHSP=発達障害でもありません。続いてはHSPについてみていきます。
HSP(Highly Sensitive Person)とは
HSP(Highly Sensitive Person)は、米国の心理学者であるエレイン・N・アーロン博士が提唱した心理学的概念です。著書である「The Highly Sensitive Person: How to Surivive and Thrive When the World Overwhelms You」は世界中22ヶ国語で翻訳されており世界共通の概念であることがわかります。
また、HSPの気質を持つ子供のことをHSC(Highly Sensitive Child)といいます。
HSPは、病名や疾患名ではないため、精神疾患の診断基準であるDSM-5にも掲載されていません。
周りの人の感情や気持ちに気づきやすく共感力が強かったり、刺激を過度に受けやすいといった気質を生まれ持った人、いわゆる「繊細な人」のことで、全人口の15~20%、約5人に1人はHSPと考えられています。そのHSP気質を持つ人のうち約70%は内向的で、残りの約30%が外交型に該当すると言われています。
チェックリストのうち12項目当てはまるとHSPの傾向があるとされています。
- 自分をとりまく環境の微妙な変化によく気づくほうだ
- 他人の気分に左右される
- 痛みにとても敏感である
- 忙しい日々が続くと、ベッドや暗い部屋などプライバシーが得られ、刺激から逃れられる場所にひきこもりたくなる
- カフェインに敏感に反応する
- 明るい光や、強い匂い、ざらざらした布地、サイレンの音などにに圧倒されやすい
- 豊かな想像力を持ち、空想に耽りやすい
- 騒音に悩まされやすい
- 美術や音楽に深く心動かされる
- とても良心的である
- すぐにびっくりする(仰天する)
- 短期間にたくさんのことをしなければならない時、混乱してしまう
- 人が何かで不快な思いをしている時、どうすれば快適になるかすぐに気づく(たとえば電灯の明るさを調節したり、席を替えるなど)
- 一度にたくさんのことを頼まれるのがイヤだ
- ミスをしたり物を忘れたりしないよういつも気をつけている。
- 暴力的な映画やテレビ番組は見ないようにしている
- あまりにもたくさんのことが自分の周りで起こっていると、不快になり神経が高ぶる
- 空腹になると、集中できないとか気分が悪くなるといった強い反応が起こる
- 生活に変化があると混乱する
- デリケートな香りや味、音、音楽などを好む
- 動揺するような状況を避けることを、普段の生活で最優先している
- 仕事をする時、競争させられたり、観察されていると、緊張し、いつもの実力を発揮できなくなる
- 子供のころ、親や教師は自分のことを「敏感だ」とか「内気だ」と思っていた
引用:『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』エレイン・N・アーロン [著]・冨田香里 [訳]
HSPの特徴的な特性「 D.O.E.S.」
アーロン博士によると、HSPの人は内向的、外向的に関わらず4つの特性があるとしており、頭文字をとって「DOES」(ダズ)とよばれています。
1) Depth of Processing(情報処理の深さ)
考え事をする時間が長く、過去のことと関連付けたり、あらゆることを想定して情報を処理します。「自分の言葉で相手がどう思ったか」などあれこれ考えても結論が出ないことも考えてしまい、他のことが手につかなくなったりしてしまいます。
2) Over Stimulation(刺激に対し敏感)
外部からの刺激に過敏なため、光や音、匂いといった外部からの刺激に感覚が敏感になります。混雑した電車や、騒がしい空間などが疲れてしまうため、1人の安心して落ち着く空間を求めます。
3) Emotional Responsiveness & Empathy(感情の反応が大きく、共感性が高い)
共感性が高いため、人の気持ちに引きづられてしまうことも。他者に感情移入しやすいのも特性です。自分とは関係ないことでも、悲しいニュースで傷ついてしまったり、自分のことのように感じてしまいます。
4) Sensitive to Subtleties(些細なことに気づく)
人が気づきにくいことに気づいたり、他者の言動にも敏感です。話し声や相手の感情を読み取ることができる反面、色々なことも考えてしまいます。
HSPに由来する感覚過敏は、いわゆる「繊細さ」であるのに対し、冒頭に挙げた感覚過敏は「五感の感覚を人より敏感に感じる」という点が異なります。
HSS型HSPはギフテッド?
ネットで「HSS型HSP」という表現をよく見かけますが、HSS(High Sensation Seeking = 刺激追求型)は、HSPとは別の概念です。提言者もアーロン博士ではありません。HSSという概念はマービン・ザッカーマン氏(Marvin Zuckerman)が提言した「強い刺激を求める人」のことを指します。
この二つを組み合わせて「HSS型HSP」と表しています。
HSSの特徴としては以下のようなものが挙げられます。
- 多様で斬新で複雑な経験を求める
例)好きだとわかっている場所にもう一度行くよりは、好きにならないかもしれないが新しい場所に行きたい。
普通でないものを見ると、とことん追求したくなる。 - スリルと冒険を求める
例)スキーやスカイダイビングなどスリルを味わえるスポーツをしてみたい。
探検家になりたい。 - 脱抑制と衝動性
例)私が何をしでかすか予測つかない、と友人は言う。
高揚感を与えてくれる成分を摂取するのが好き。 - 退屈しやすさ
例)会話によっては、とんでもなく退屈する事がある。
する事もなく待つのが嫌。
毎日同じ人と一緒にいると飽きる。
どうでしょう、常に刺激を求めたり、好奇心旺盛なところはギフテッドの特性ととても似ていると思われたのではないでしょうか。ここからは持論になりますが、HSP=ギフテッドではないことからも、イコールではないと思いますが、ギフテッドとHSS型HSPはとても近いところにあるのではないでしょうか。
HSE型HSP
また似たアルファベットが並んでいるので混同してしまいそうですが、こちらは「外向型HSP」とよばれるものです。
HSEとは「The highly sensitive extrovert 」(非常に敏感な外向型)のことです。
HSEとHSPは相反する特性だと思われるかもしれません。このタイプのHSPは社交的でありながらも繊細さを持っていため、人付き合いをしすぎて結果的に疲れてしまうことがあります。
以上をまとめると下記のようになります。「ギフテッド」とは同じ特性の部分もありますが、ずば抜けた才能に関しては定義に含まれていないので、ギフテッドの中にはHSPの人もいる。ということになると思います。
HSS型HSPは、興味関心は外部に向いており、外部に刺激を求めるが、社交的ではない「刺激追及型の繊細さん」
HSE型HSPは、社交的で人との関わりを持つことが好きな「外向型な繊細さん」
参照 The Highly sensitive person
ギフテッドの過興奮性(OE)
では続いてギフテッドの感覚過敏についてです。ギフテッドは過興奮性(OE)という特性を持っていると言われています。
この特性の一つ、「知覚性の過興奮性」が高い場合は、見る、嗅ぐ、味わう、触れる、聞くなどの感覚が増長されたものとなり、とても感覚過敏と似た症状がでます。
ギフテッドの過興奮性の症状もタグを嫌がったり、味覚に敏感だったりもしますが、ギフテッドの知覚性過興奮性については「感性の鋭さ」もあるとされています。
絶景に息をのんで涙をしたり、音楽や美術、自然などに感動するといった美的感覚にも通ずるとされています。この点は冒頭で挙げた五感の「感覚過敏」とは異なる点ですが、この点はHSPの特性には記載があるためHSPと似ていることがわかります。
OEについてはこちらの記事に記載しています。
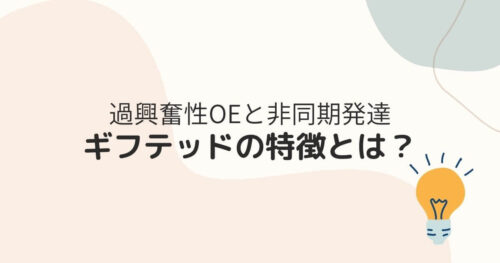
発達障害・HSP・ギフテッドの感覚過敏の違いと共通点
ここまで比較してきましたがいかがでしょう。
「感覚過敏」という症状についてはどれも似ており共通しているように思いますが、感覚過敏=発達障害=HSP=ギフテッドではないことがなんとなくお分かりいただけたのではないでしょうか。
HSPが全人口の15~20%、約5人に1人はHSPと考えられているのに対し、ギフテッドは人口の2〜5%、50人に1人とされているのでその点でも異なることがわかります。
また息子に関しては、HSPの気質はあまり当てはまりません。真逆の項目もいくつかあります。
HSPを提唱したエレイン・N・アーロン博士自身は、自身のHP内の「Is Sensitivity the Same as Being Gifted?」というコラムで、HSPとギフテッドについて述べています。
「すべての才能のある人が非常に敏感であるわけではありません。私は才能のある非HSPを多く知っています。」また、「すべての非常に敏感な人々が才能があるわけではない」と言っています。
実際、OEの特徴ととHSP自体は非常に似ているとしていますが、ギフテッドかどうかを判別するには、いくつかの共通の行動特性があります。幼少期から早熟かどうか、特定の分野で並外れた才能を発揮していたかなど、子供がギフテッドかどうかは観察する必要があるとしています。
参考図書 敏感すぎる私の活かし方 高感度から才能を引き出す発想術 (フェニックスシリーズ)
息子の感覚過敏と鈍麻
息子の場合は、感覚過敏と鈍麻の両方を持っています。
過敏な部分に関していうと、国立障害者リハビリテーションセンターの調査の通り、聴覚が最も敏感です。
しかし、聴覚過敏の子にとって、電車の音やスピーカーの音、運動会のピストルの音などは恐怖となりますが、息子はそういったことはなく、むしろ聴こえてくる生活音(駅メロや信号機の音など)を楽しんでいます。
そのため、耳に関しての敏感さはどちらかというとギフテッド由来の過興奮性(OE)によるものなのかなあと思っています。「いい音」に興奮する反面、音が外れているのを気持ち悪がったり、調が嫌いだったり、そういった好き嫌いがあるようです。
触覚に関しては、タグを嫌がったりはしませんでしたが、体が熱くなることが嫌いなようです。
家の中では靴下を嫌がり、直ぐ脱ぎます。靴下だけではなく服も家の中ではほぼ着ず、真冬もタンクトップ一枚で過ごします。
お風呂の湯船も出た後に体が熱くなるのが嫌だそうでほぼ浸かりません。お風呂は濡れるのが嫌で一時期入りたがらない時期がありました。爪切りも切った後の感覚が苦手で、11歳ごろまで嫌がっていました。12歳になると、自らマイ爪切りを購入し、自分で切るようになりました。
この点は、先述の、自閉スペクトラム症(ASD)のある人ではない人に比べて触覚が一番辛いと答えた人が多いという点から自閉スペクトラム症由来かもしれません。
味覚に関しては、酸っぱいものや、りんごや梨といった食感がシャリシャリしているものは食べません。
炭酸飲料も周りはみんな飲んでいる中、中学生になった今も飲めません。
視覚と嗅覚に関しては、育てていて特に何かを嫌がることも過敏さも感じたことはありません。
一方、鈍麻に関しては、生まれてから一度も予防接種や採血で泣いたことはありません。
小さい頃から、転んでも泣かなかったので、痛みに関しては鈍麻なところがあると思います。この鈍麻に関しては、自閉症スペクトラム(ASD)の診断の一つであると米国精神医学会の診断基準(DSM-5)に記載があることを踏まえると、ASD由来かもしれません。
ただし、痛みに関しては鈍麻なのですが、ギフテッド由来の想像性の過興奮性があるため、痛くないけれど鉛筆の芯が刺さったりすると「この世の終わり、もう死ぬのではないか」と大騒ぎすることはありました。
このように今まで育ててきて息子のようすを改めて振り返ると、ASDによる感覚過敏と感覚鈍麻と、ギフテッドの特性(OE)による感覚の過興奮性とが様々に影響しあって生活のしづらさや困難を感じているのではないかと思いました。
また、以下のようなデータもあります。
高IQ・高知能は心理学的・生理学的に危険因子になる

この図はアメリカのメンサ会員 3715人を調査した研究で、参加者にグラフの左側から、気分障害、不安障害、注意欠陥多動障害(ADHD)、自閉症スペクトラム障害(ASD)、食物アレルギー、環境アレルギー、喘息、自己免疫疾患などの生理学的疾患の診断済みおよび/または疑いの有病率を自己申告するよう求めその結果をグラフにしたものです。
全国平均統計と比較した場合、メンサグループの方が不安障害、アレルギー、喘息、自己免疫疾患などの症状を抱える可能性が一般的なIQ値の人よりも高かったという結果を表したものです。
つまり、知能の高い人は心理的および生理学的障害を経験するリスクが著しく高いということを意味しており、高い認知能力を持つ人は、環境に対して過度の反応を示すと仮定しています。
同じような内容として、「ギフティッド その誤診と重複診断: 心理・医療・教育の現場から」に、ギフテッド児はアレルギーや喘息といった免疫障害を抱える傾向が高いとされており、その結果、イライラして多動傾向が見られたり、癇癪を起こしてり、衝動的になってしまうこともあるとのこと。
これがADHDや反抗挑発症と誤診されやすいとも書いてあります。
また高IQ・高知能の場合、中枢神経系が過度に興奮し、過剰に反応する傾向があるとの研究結果もあります。
心理学研究レポートを掲載しているインテリジェンス誌の「High intelligence: A risk factor for psychological and physiological overexcitabilities」によると、高い知的能力を持つ人は、さまざまな領域で過剰な興奮を持っており、不安障害や、感覚の亢進、免疫反応や炎症反応の変化を伴う生理学的危険因子になる可能性があるとしています。
シルバーマンによるデータによると、通常の子供のアレルギーの割合は20パーセントであるのに対し、IQ160以上の子供は44%だったとの調査結果があり、ギフテッド児は人一倍激しいという特性があり、これが、交感神経系や中枢神経系に影響を与えている可能性があるとしています。
花粉アレルギー
息子は3歳でスギ花粉アレルギーと診断されています。あまりにも鼻水が長引き、めやにも酷かったため、血液検査をして判明しました。
私も、主人も花粉アレルギーではないので、「3歳の子がもう花粉症になるのか!」と驚きました。
アレルギーに関しては、ギフテッドは知能との関係は明らかではないものの、自身の内外の刺激に敏感であり、アレルギーの割合は高い。とギフティッド その誤診と重複診断: 心理・医療・教育の現場からに記載があります。ギフテッドの過敏さはアレルギーという面でも出るようです。
配慮のポイント
感覚過敏があり、生きづらさを感じた場合は、現在の医学では、感覚過敏を治療することはできないため、一つ一つの症状に対処していく方法をとることが多いようです。
対処方法としては、苦手なことを無理強いするのではなく、軽減させるための工夫を考えて試していく方が良いとされています。
一人ひとり特性を踏まえた対応方法を見つけることで、「生きづらさ」を「生きやすさ」を変えていくようにします。
・直そうとするのではなく、人とは感覚が異なることを説明し、その特性と付き合っていけるように本人に説明する
・スモールステップによる支援(少しずつ成功体験を重ねていくなど)
・感覚過敏がある場合は、音や室温など感覚面の調整を出来る範囲で行う
・日常生活に不自由なレベルの場合は専門家などに相談する
・感覚よりも行動を優先出来るようになるタイミングまで見守る
聴覚
騒音が気になる場合は、イヤーマフを活用する方法もあります。デジタル耳せんは、騒音はカットし人の声だけ聞こえます。電車内でもアナウンスだけ聞こえて環境騒音はカットするので落ち着いて乗っていられます。
触覚
感覚過敏のため、マスクが付けられないという子も多いと思います。心地いいものを身につけるというのも対処方法の一つです。
どうしてもつけられない場合は周囲に理解を求める缶バッチなどもあります。
嗅覚・視覚・味覚
嗅覚過敏の場合は、マスクをして匂いを防いだり、お気に入りの香りを持ち歩くといった対応があります。
視覚過敏の場合は、メガネやサングラスをかけて目からの刺激を抑えるのも方法の一つです。
味覚過敏の場合は、苦手なものは無理に食べないようにしたり、調理方法を工夫するといった方法があります。
ヘルプマークも最近は良く見かけるようになりました。これは外見からはわからない障害があったり、援助や配慮を必要としている人向けに東京都が2012年から取り組みをはじめました。今現在多くの都道府県で配布されるようになり、周囲の人に配慮が必要であることを知らせることが出来るようになりました。配布場所は、各自治体によって異なりますが、保健センターや市区町村の担当窓口でもらえます。Amazonにもいろいろなタイプが売っています。
HSP
HSPの場合は感覚過敏に対しての対処に加え、人との関わり方も工夫することで生きづらさを軽減できます。HSPは自分が思っている以上に疲れやすい傾向があります。疲れやすい人や物とうまく距離を取ることも大切です。
また自分なりのリラックス方法をいくつか見つけておくことも対処方法となるでしょう。
まとめ
一言に「感覚過敏」といっても原因は人によって異なります。また感覚過敏だから発達障害、HSP、ギフテッドだと断定するものではありません。
大切なのは感覚過敏によって何かしらの生きづらさを感じているのであれば、頑張って治そうとするのではなく、自分の気質や特性を受け入れ、その特性とうまく付き合っていく方法を考えたり、楽になる対処方法を試して、生きづらさを軽減させていくことなのではないでしょうか。