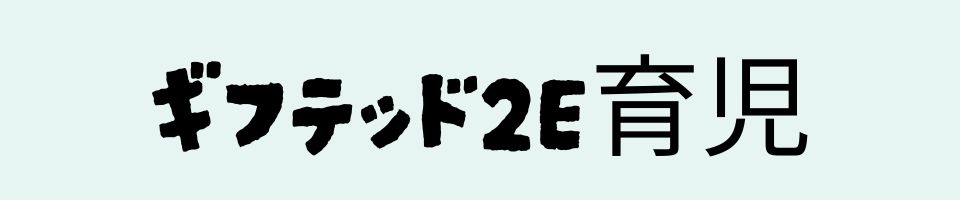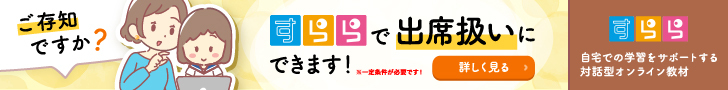ギフテッドとADHDの違いは?
似ている特徴があるようだけど…
昨今、ギフテッドもADHDも耳にする機会が増えました。結論から言うと、ギフテッドとADHDは異なるものなのですが、特徴が似ているため、見分け方が難しいようです。
実際に私自身も育てていてADHDかもしれないと思い、地域の支援センターに相談したことがあります。
幼稚園や学校の先生から問題行動を指摘され、検査をしたらギフテッドだったというケースもあります。そして、医療現場では症状だけで診断してしまい、ギフテッドとはわからず発達障害と誤診されることも。
今回は「ギフテッド」と「ADHD」二つの違いについて我が家のケースをあげてご紹介します。
ADHD(注意欠如・多動症)とは
ADHD(注意欠陥・多動症)の特徴として大きく、「不注意」と「衝動性」が挙げられます。
「不注意(活動に集中できない・気が散りやすい・物をなくしやすい・順序だてて活動に取り組めないなど)」と「多動-衝動性(じっとしていられない・静かに遊べない・待つことが苦手で他人のじゃまをしてしまうなど)」が同程度の年齢の発達水準に比べてより頻繁に強く認められること
引用元 厚生労働省HP ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療
厚生労働省のホームページによると、こういった特徴が持続的に認められ、そのために日常生活に困難が起こっている状態で、12歳以前からこれらの行動特徴があり、学校、家庭、職場などの複数の場面で困難がみられる場合に診断されます。
先天的なものなので、急に発症するわけではないのですが、「落ち着きがない」「常に体を動かしている」「ずっとしゃべっている」など、ほかの子とちょっと違うかもしれない。といった違和感で親が気付くケースが多いようです。
不注意症状の具体的な例としては以下のような行動が挙げられます。
・授業や会話などに集中し続けることができない
・気が散ってしまう
・ミスや無くし物が多い
・話しかけられても上の空になりやすい など
多動性・衝動性症状の具体的な例はこちら。
・じっとしていることができない
・授業中に席から離れる
・落ち着かない
・動きが多い
・突発的な言葉や行動が多い など
参照 Medical Note
ギフテッドとは
ギフテッドとは、生まれつき知性が高く、突出した能力を持つ人のことです。周りの同世代の子供より成長が早かったり、一般的な成長過程と異なるため、「ちょっと周りと違うかも」と親が気づくケースがあります。
また、努力して優秀な成績を修める「秀才」とは異なります。先天的とされているため、後天的に「ギフテッドになる」ということはありません。
「ギフテッド=天才」と称されることもありますが、「万能な天才」というよりは、多くのギフテッドは「特定の分野において突出した能力があるが、支援が必要な子」です。
ギフテッドについての定義は国や地域によっても定まっていません。
ギフテッドの特徴についてはこちらに詳しく記載しています☟
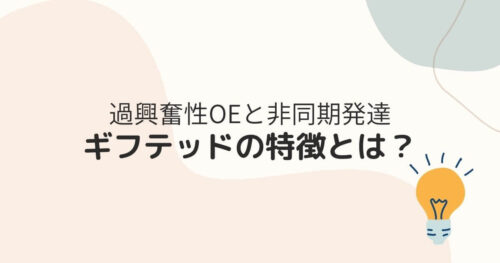
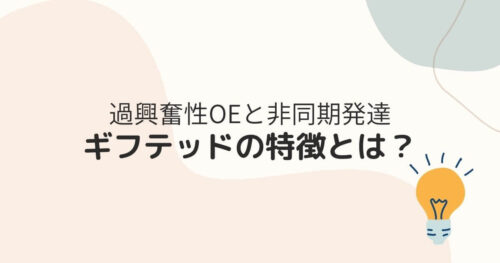
ADHDかもしれないと思ったきっかけ
息子を育てていて「ちょっと特性があるかもしれない」と思ったきっかけは、幼稚園年長さんの最後の発表会の時のこと。
みんな真面目に楽器を演奏している中、ヘラヘラ横を向いて終始笑いながら演奏をしていました。
この姿を見て、これはADHDの「多動」の症状かも?と思ったのがきっかけでした。
幼少期から、レストランではゆっくり食事ができない、電車での移動が大変、など育てていて「落ち着きがない」「じっとしていない」という感覚もありました。
ただ、日々の活動で忘れっぽいとか、飽きっぽいと思うことはなく、むしろ、好きなことをしているときは過集中が見られました。
男の子にしては、幼稚園の出来事など色々お話をしてくれるタイプでした。おしゃべりなタイプではありましたが、人の話を聞かないでしゃべり続けたり、割り込んで話すようなことはありませんでした。
また、幼稚園のクラス活動の時も、じっとはしていませんが、輪から飛び出たりすることはなかったようです。
当時、気になった私は図書館に通い詰めて、発達障害にまつわる本を読み漁っていましたが、当てはまるような、なんか違うようなそんな感覚でした。
幼稚園3年間修了後、地域の療育センターへ
小学校に入学する前にもし診断名がつくなら診断してもらい、多少なりとも配慮をしてもらったほうが学校生活がスムーズに始められるのではないかと思い、地域の発達支援センターに電話をしました。
たまたま直ぐに予約がとれたので、療育センターのケースワーカーの方と常駐しておられる小児科医と面談しました。その際に「新版K式発達検査2001」も検査しました。
発達検査とは
発達検査は、発達全般、および認知、言語・社会性、運動などの子どもの状況を客観的に測定する検査です。結果は、いわゆる「健常児」ではどのくらいの年齢に相当するかという発達年齢、発達年齢と実際の年齢である生活年齢との比率を求めた発達指数(=DQ、年齢どおりに発達していれば100)で表現されます。
発達指数は、知能、歩行・手作業などの運動、着衣・飲食などの日常生活、ままごと遊びなどの対人関係の発達など、子どもの広い範囲の発達を対象とした指標です。
引用元 てんかん情報センター
発達指数はDQといって、子供の発達の基準を数値化したものであり、IQ(知能指数)とは異なります。
検査の結果、多動と衝動が多少あるので、学校に伝えてもいいと思いますが、年相応だと思います。とのことでした。
一度の受診ではわからないのでその場では発達障害とは診断されませんでしたが、それでも母親の私は日々の行動の特徴からいわゆる「グレー」なのかなと思っていました。
ギフテッドとADHDどっち?
そして月日は流れ、学校での問題行動が目立つようになり、また発達障害を疑い小学生4年生で発達検査を受けます。WISCを受けた後に、ADHDとギフテッドの違いとして医師に言われたこととしては



ADHDの場合は場面を選ばず、どんなときも多動になります。
息子さんの場合はいつもというわけではなく、息子さんの話を聞くと理由があって多動になっている(例えば授業がつまらない、退屈、やることがないから手遊びをするなど)のでまたちょっと違います。
当時、ギフテッドという知識がなかったので、私は息子のことを「ADHDかもしれない」と思ったのですが、ギフテッドとADHDはどちらも衝動性、多動が共通してみられるそう。
ただ、同じように見える「多動」でも、ADHDの場合は、いかなる状況下でも問題が生じるのに対し、ギフテッドの場合は、何らかの意図や理由があって多動が生じるとのことでした。
また、ADHDは診断名であるのに対し、ギフテッドは診断名や障害の病名ではないので、ここが大きな違いになります。
そしてさらに、このようなことを言われます。



息子さんはADHDよりもASDといった要素を持ち合わせた2Eだと思います。
「2E」というのは、「ギフテッド」+「ADHD」、「ギフテッド」+「ASD」、「ギフテッド」+「LD」といった、発達障害の症状を併せ持つ子のことです。ギフテッド児は、知的障害を例外として、ADHD(注意欠陥多動性障害)やASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)などの発達障害にもなるとされています。
つまり、ギフテッドかADHDかどちらかではく、両方を持ち合わせていることもあります。
そのため、見極めが難しく、知識が十分ない医師の場合、誤診されてしまうことがあります。
2Eについてはこちら☟
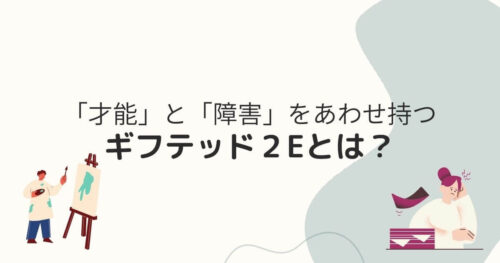
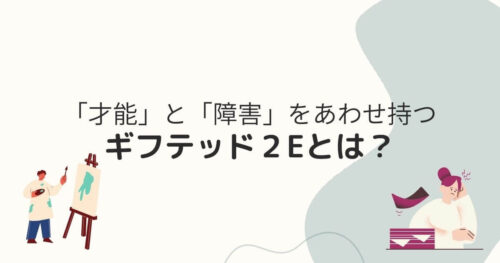
2019年に春秋社から出版された「わが子がギフティッドかもしれないと思ったらー問題解決と飛躍のための実践的ガイド」(ジェームス・T・ウェブ 著、ジャネット・L・ゴア 著、エドワード・R・アメンド 著、アーリーン・R・デヴリーズ 著、⻆谷 詩織 訳)によると
子供の知能が高い場合、ギフティッド児に関する訓練と経験を積んだ専門家による評価を受けるべきだ。これは重要な警告だ。なぜならADD/ADHD児の行動特性は、創造性やギフティッドネス、あるいは過興奮性に起因する典型的な特性と似ていることが多いが、創造性やギフティッドネス、過興奮性に起因する特性に対する的確な介入はADD/ADHD児への的確な介入と異なるためだ。
教育環境やカリキュラムの調整の努力がなされていない状態でのADD/ADHDの評価を専門家に依頼するのは概して時期尚早だ。
との記載があります。ADHDによる特性なのか、ギフテッドによるものなのかを誤診されてしまうことは、本人にとっても周りの関わる人にとっても深刻な問題であるとしています。
どちらに起因しているかによって、支援方法が異なるため、慎重に判断する必要があります。
ギフテッドとADHDの違いと共通点
このようにギフテッドとADHDは類似している点が多いのですが、同じに見える行動も発達障害の枠組みだけで考えるのではなく教育環境が合っていない可能性に目を向けるよう、シャロン・リンドはADD/ADHD診断に連れていく前に親が慎重に吟味すべきチェックリスト15項目というものを作成しています。
「もしかしたらADHDかも?」と思っておられるご家族や先生や支援者の方がいらっしゃいましたらその前に、一度下記のチェックリストをご参考に、教育環境を変えてみるのも一つだと思います。
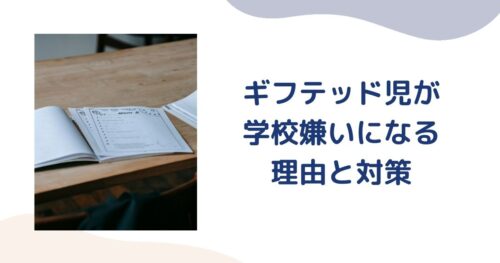
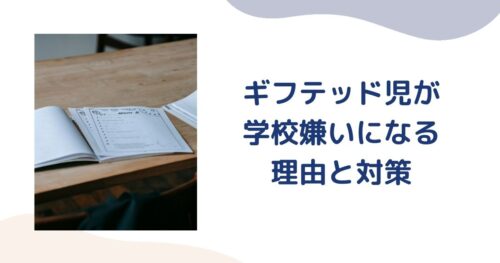
友達関係について
ギフテッド児は知的レベルが同世代の子と合わず、話が噛み合わないことがあります。そのため、友達と仲良くできなかったり、輪に入ろうとしないことがあります。
行動について
不適切な行動は、ギフテッドの場合は、理解してもらえなかったり、暇だったりと理由があって不適切な行動をすることが多いです。
学習面に関して
ギフテッドの場合は、知的好奇心が旺盛です。学校のようにみんなと足並みをそろえて学んでいくスタイルだと物足りず、不適切な行動をすることがあります。
つまらない授業はあえて他のことをしていることもあります。先生には話を聞いていないように見えるため、わざと問題を当ててくることもあるそう。



他のことしてても僕は全部聞いているから、正答してしまって先生はなんか残念そうなんだよね。
と言っていることもありました。
このように不適切な行動に関しては、ギフテッドの場合は意図があることが多いです。
このように、同じに見える不適切な行動も起こるメカニズムが異なるとされています。
参照 permitted to translate: Lind, S. (2011). Before Referring a Gifted Child for ADD/ADHD Evaluation.
http://sengifted.org/before-referring-a-gifted-child-for-addadhd-evaluation/
https://haruaki.shunjusha.co.jp/medias/RIHrj/uploads/files/kiyo39_2_07.pdf
日本語版 角谷詩織
困りごとや生きづらさを感じたら
ADHDによるものなのか、ギフテッドによるものなのかなかなか親ではなかなか判断は難しいので、少しでも生きづらさを感じているようであれば専門機関の受診をお勧めします。
最初にかかる相談機関としては、発達障害を専門に診る小児科や児童精神科でもよいのですが、発達支援センターや、家庭支援センターなどでも相談にのってくれます。病院は何か月待ちというところも多いため、まずは地域の発達支援センターなどに問い合わせてみてもよいと思います。